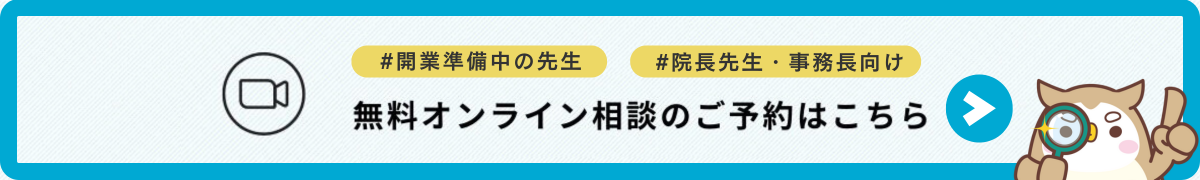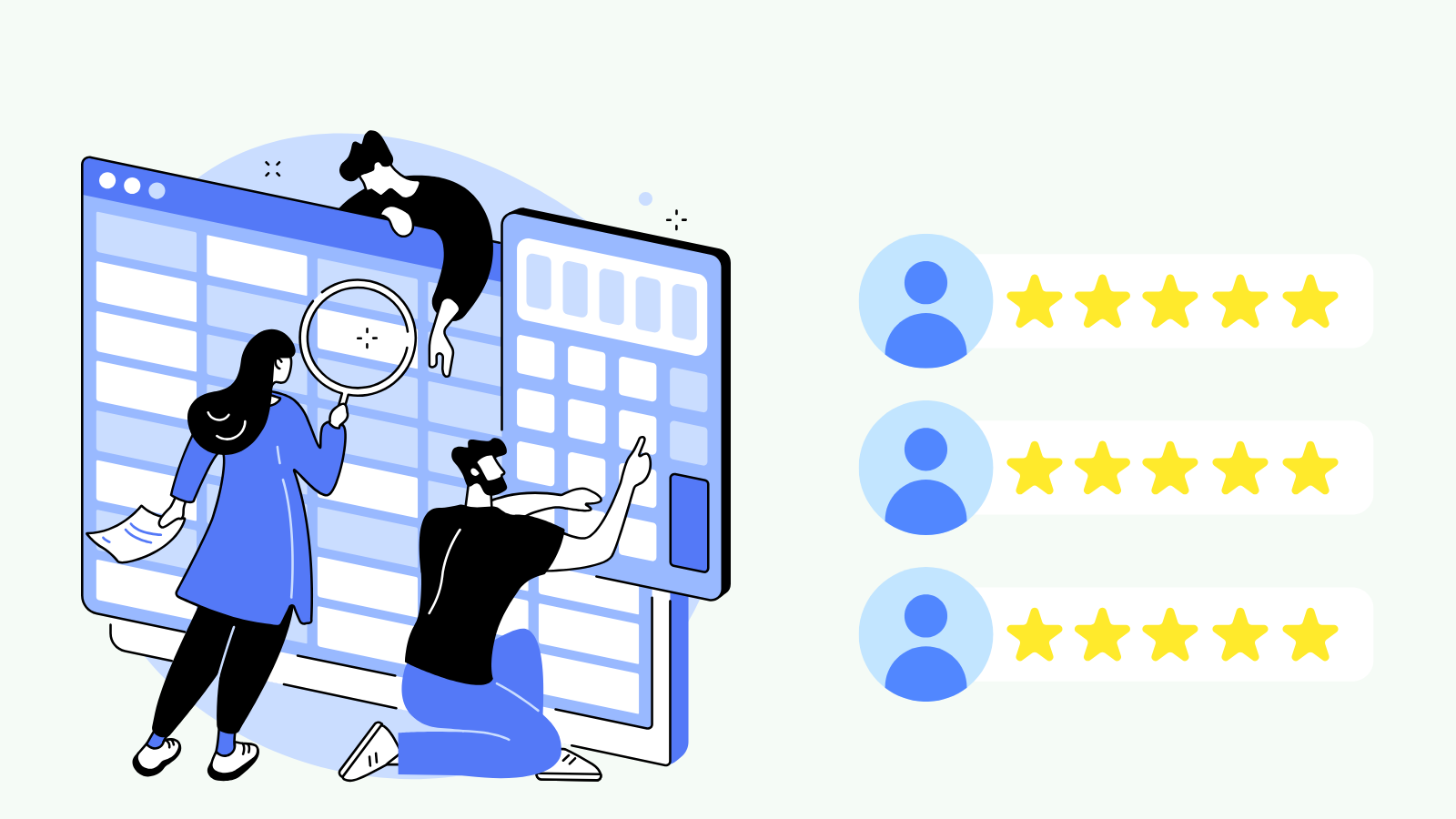
2025.04.02
集患と口コミ対策に必須!「顧問のWeb担当・ホームページ管理者」がクリニック成功の鍵
「集患に力を入れているのに、なぜ患者が集まらないのか?」
「もめやすい。トラブルを起こす可能性のある患者さんが最近増えている気がする。。。」
その原因は、クリニックのホームページが正しく機能していないからかもしれません。
多くのクリニックではホームページを開設しているものの、情報が古かったり、患者さん目線に欠けていたりすることがよくあります。
結果として、悪い口コミが増え、集患に逆効果となっているケースも。
本記事では、クリニックが直面している集患・口コミ問題を解決するための対策をご紹介します。また、顧問のWeb担当者やホームページ管理者の役割および、適切な導入方法について詳しく解説します。
自己満足型のホームページになっていないか要チェック
「集患したい」と考えているクリニックほど、ホームページのインフラ整備が不十分なケースが多いのが実情です。
実際、「どのような診療をしているのか」が正確に発信されていないクリニックは少なくありません。
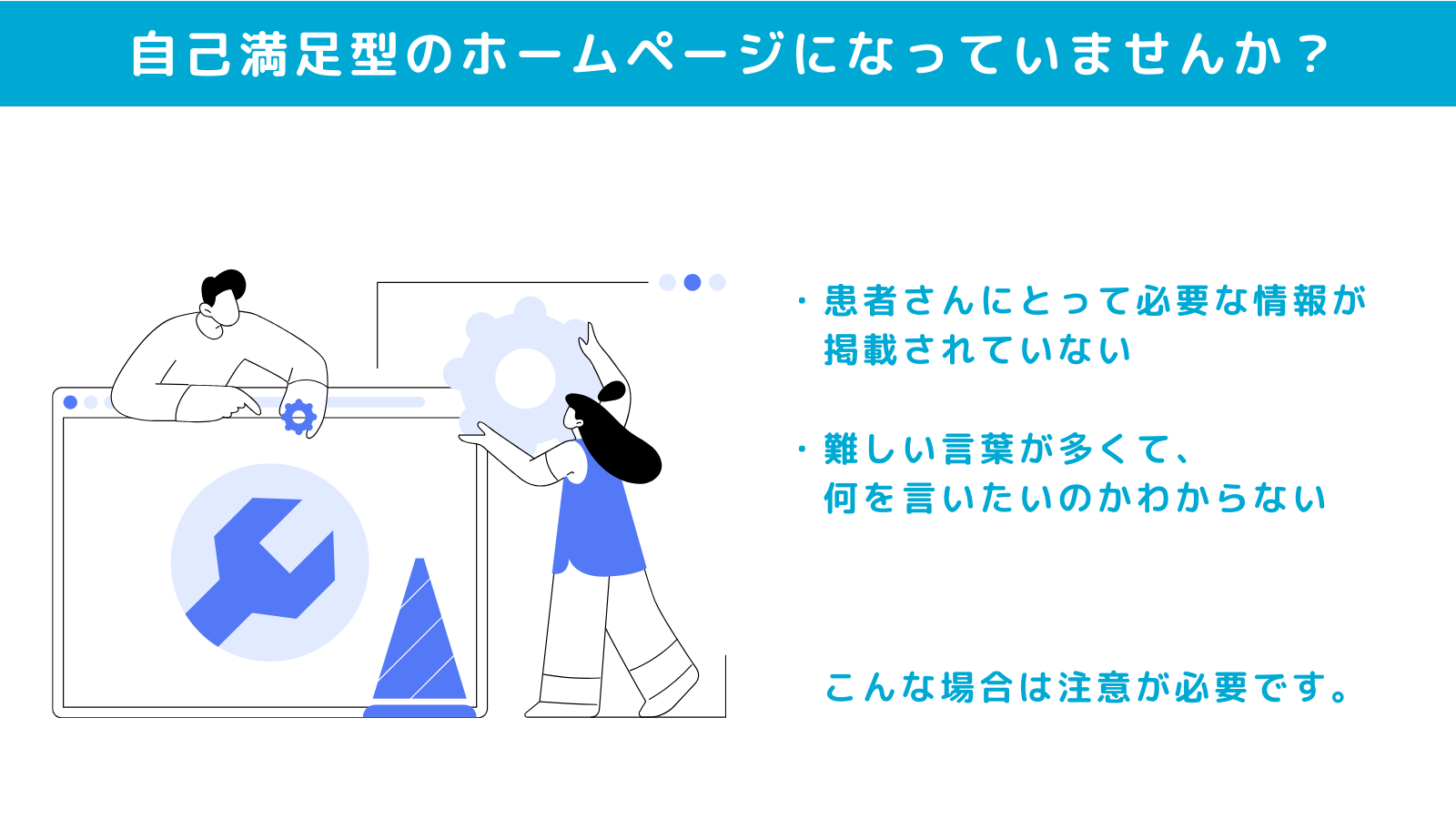
患者さんにとっては「自分が受けたい治療があるのか」「料金は適正か」などの具体的な情報が重要ですが、クリニック側の視点で情報が書かれているため、結果的に患者さんとの意思疎通が取れず、ミスマッチが生まれています。
例として、ホームページに書かれている内容が専門用語ばかりで、患者さんには理解しにくいケースが目立ちます。
「難しい言葉が多くて、何を言いたいのかわからない」と感じる患者さんも多く、「自己満足型」のホームページになっていることが原因で集患に悪影響を及ぼしているのです。
その結果、患者さんが一番知りたい情報が埋もれてしまう。(見つかる前に、見る気が失せてしまう。)この場合、患者さんは「まあ、いいや。行けば全部何とかしてくれる」の状態で来院するので、非常にミスマッチの起こりやすい事例となります。その結果「思っていた診察をしてくれなかった。」が起こりやすいのです。
また逆に、実は患者さんにとって有益な診療を行っているにもかかわらず、ホームページには載っていない。(裏メニューとなってしまっている。)「こんな治療をやっているなら、もっと早く通いたかったのに。」と患者さんに思われてしまうことは、クリニック側にとっても大きな機会損失に繋がります。
口コミ対策をしよう!話を盛らないことが信頼につながる
たびたび問題になる口コミ対策ですが、弊社宛にも「対策方法」の相談はよくされます。
まず結論から申しますと、「ありのまま、良い口コミを書いて頂ける患者さんを1件1件地道に増やす」が正解です。
2週間に1件、難しい場合は1ヶ月に1件でも構いません。(1ヶ月に1件頑張れば1年で12件、2年で24件も増えます。)

書いてもらう方法は単純で「プライドを捨てること」これに尽きます。
良い口コミを書いてくれそうな患者さんに「実は口コミで困っている」と相談することでコミュニケーションも図れます。ぜひ話しやすい患者さんから順に医師の方から「相談」してみてください。
またやってはいけないこととしては、「話を盛った口コミを強要しないこと」です。
クリニックのホームページで自院をよく見せたいという気持ちは理解できます。しかし、過剰なアピールはかえって逆効果になることがあります。診療内容やサービスを必要以上に良く見せてしまうと、実際に来院した患者さんが「思ったより良くなかった」と感じることになり、不満が悪い口コミとして表面化します。
特に、「最新の機器を導入しています」「〇〇治療に特化」などは誇張表現が多いと、患者さんは期待値を高く持ちます。
結果的に、「何が良いのかわからない」と実際の治療内容とのギャップが生まれ、口コミで「期待していたほどではなかった」と書かれてしまうのです。ホームページで清潔感や安心感を演出することは大切ですが、「適切な表現。ありのままを伝えること」が最も重要です。
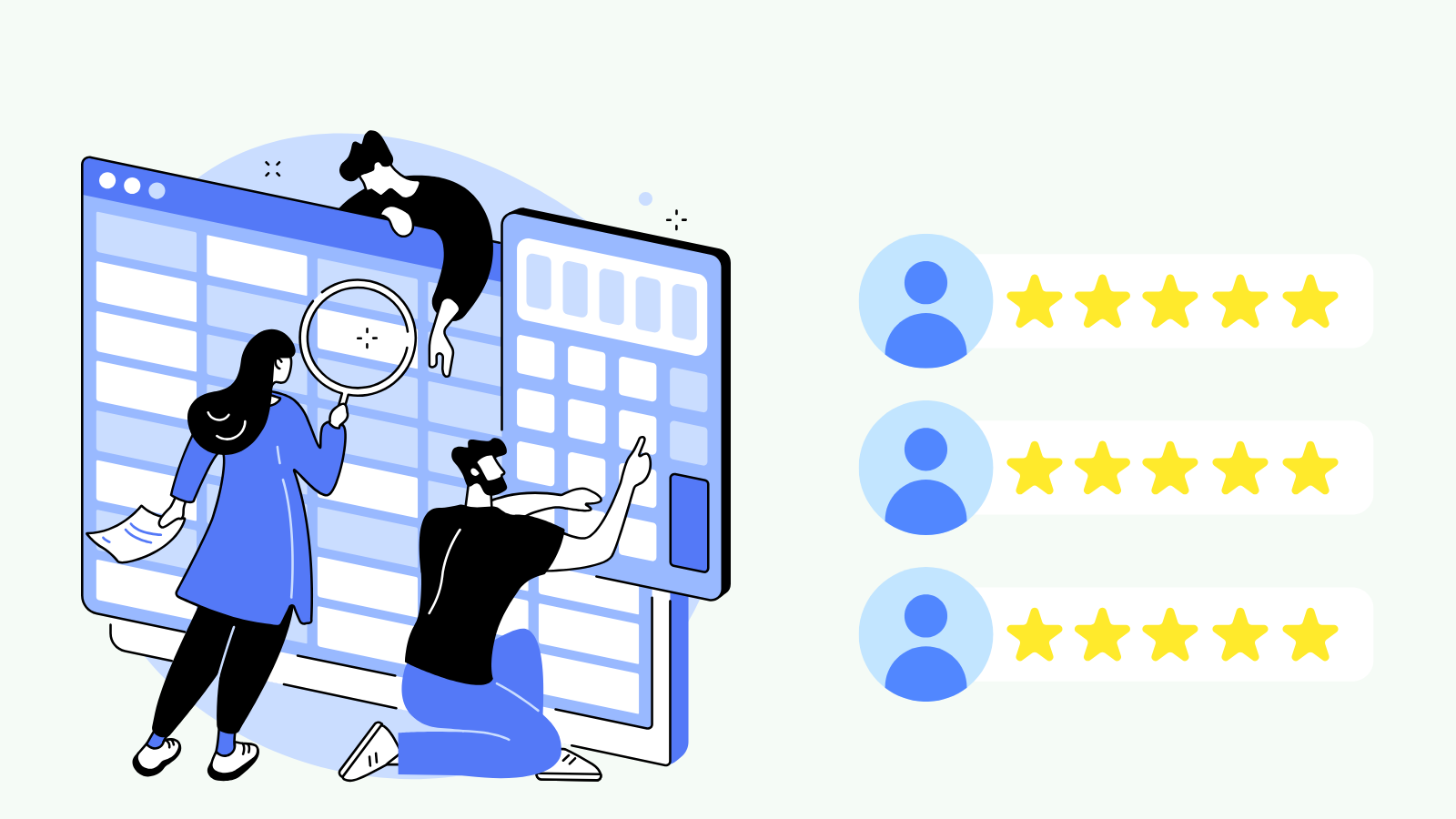
「期待通りだった」「思っていた以上に良かった!」と思われることが、長期的に信頼を築く鍵となります。
無理に背伸びをせず、誠実な情報発信を心がけることが、結果的に良い口コミを増やすことにつながります。
顧問のWeb担当・ホームページ管理者を設けることの重要性
別記事(クリニックホームページはインフラ整備が重要!放置のデメリットやトラブル防止対策を紹介)でもご案内しておりますが、クリニックの運営に集中するためには、第三者視点を持ったWeb担当者を導入することもおススメです。
ホームページのインフラ整備や定期的な更新、法改正への対応など、クリニック側が対応しきれない領域をカバーする存在が必要だからです。
特に医療業界では、法改正に伴ってホームページの記載内容を変更しなければならない場面もあります。2024年6月に施行された診療報酬改定のように、書面掲示事項をホームページに反映しなければならないケースが増えているため、法的な要件を正確に満たす対応が求められます。これをクリニック側だけで対応するのは負担が大きく、間違いが生じるリスクも高まります。
また、「患者さん目線での情報発信」もWeb担当者の重要な役割です。
クリニック側にとっては当たり前の情報でも、患者さんにとっては初めて知ることが多いため、専門用語を避けてわかりやすく説明することが重要です。外部の専門業者に委託することで、第三者視点での冷静な判断が可能になり、患者さんとの認識のギャップを埋めることができます。
どのようなWeb担当者・管理者を導入すべき?
適切なWeb担当者を選ぶ際には、専門用語を多用せず、わかりやすく説明できる人が理想です。医療業界では専門用語が飛び交うことが多いため、患者さんにとって理解しにくい表現になりがちですが、あくまで患者さん目線で説明できる担当者が望ましいでしょう。
また、単発の対応ではなく、長期的な関係を築ける担当者が必要です。
「担当者が辞めてしまって何もわからなくなってしまった」と弊社に相談が来るケースも多々ございます。ホームページは一度作って終わりではなく、定期的な更新や修正が必要になるため、信頼できるパートナーを見つけることが重要です。
「なんとなく」で対応するのではなく、患者さんの反応やアクセス数などのデータを基に分析し、的確なアドバイスをしてくれる担当者が理想的です。加えて、院長やスタッフとしっかり意思疎通が取れることも重要なポイントです。クリニックの内情を理解しつつ、第三者目線で的確なアドバイスをくれる担当者がいることで、ホームページを効果的に活用し、集患や口コミ対策に直結させることが可能になります。
まとめ
- ホームページのインフラ整備不足が集患や患者さんの不信感につながるため、定期的な更新とメンテナンスが重要。
- 過剰な表現や誇張は悪い口コミの原因になるため、患者さん目線で誠実な情報発信を心がける。
- 第三者目線を持ったWeb担当者を配置することで、インフラ整備や法改正対応がスムーズになる。
- 長期的な視点で改善できる担当者を選び、患者さんとのミスマッチを防ぐことで信頼関係を築く。
「正しい情報発信」と「誠実な対応」が患者さんの信頼を生み、自然と良い口コミや集患につながります。適切なWeb担当者を配置し、ホームページのインフラ整備を徹底することで、クリニックの運営を安定させていきましょう。
■著者 Kurumi株式会社
WEBサイト:https://kurumi.co.jp/
東京都豊島区に拠点を置くWeb制作会社。
病院やクリニックに特化し、Webコンサルティングを含めた初期費用無料・月額制のサブスクリプション型ホームページを提供している。
また「固定費を削減したい」というニーズに応え、「ホームページの月額見直し相談所®」を商標登録し、運営している。
目利き医ノ助は、販売をしない “中立な立場 ” で、全国の先生のご要望や課題に合ったシステムのご提案や選定のお手