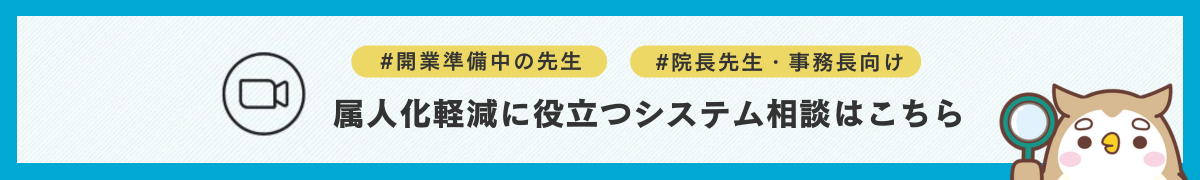2025.03.05
クリニックの院長が対応する医療安全関連義務(法令遵守)DX化でスマートに解決!
医療安全関連の法令について
「医療安全関連義務の法令遵守」と聞いて、不安を感じる先生も多いのではないでしょうか。日々の診療業務に加え、法令やガイドラインの変更に適応し続けるのは容易ではありません。ドキュメントの整備や報告義務・記録管理、スタッフの安全教育など、求められる業務は多岐に渡っており、限られた時間の中で対応するのは大きな負担となっています。整備が進んでいないクリニックも多いのではないでしょうか?
非常に多くの法令等を確認し、それに対応するのは非常に大変です。参考までに関連法令の一部を下記にご紹介させていただきます。
医療法第六条の十二
医療法第二十五条第一項
医療法施行規則第一条の十一
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第九章
医薬品医療機器等法第二条第四項
医薬品医療機器等法第二十三条
これらをしっかりと読み込み対応するのはかなり労力を要するので大きな負担になるかと思います。
診療所の患者安全管理体制の実態
昨年、2024年にプライマリ・ケア学会が「我が国のプライマリ・ケア診療所における患者安全管理体制の実態調査」を発表しましたが、安全管理体制が十分とは言えない状況であることが明らかになりました。また、この発表データは医療法によって義務化されている内容が調査項目に含まれており調査結果では社会的望ましさのバイアスが指摘されており、実際にはさらに低い実施率の可能性があります。
まず、医療法の改正に対して情報を適切に把握できていない状況や、広範囲にわたる法令を確認しないと適切な整備が難しい現状が影響していると考えられます。保健所の立ち入り前になって慌てて書類の整備を行うケースや、コンサルティング会社に駆け込むケースもよく聞かれます。
「我が国のプライマリ・ケア診療所における患者安全管理体制の実態調査」の調査結果によると、診療所における基本的な患者安全管理体制は以下の通りです。(有効回答183人)
• 患者安全担当者を設置: 51.9%(95人)
• 患者安全委員会の設置: 35.5%(65人)
• インシデント・アクシデントレポートシステムの導入: 67.8%(124人)
• 多職種に対する患者安全学習機会の提供: 59.0%(108人)
また、患者安全に係る指針の作成・更新状況は以下のようになっています。
• 医療の安全確保のための指針作成: 53.0%(97人)
• 院内感染対策の指針作成: 73.2%(134人)
• 医薬品の安全使用のための手順書作成: 38.8%(71人)
• 医療機器の安全確保の手順書作成: 32.8%(60人)
• 針刺し事故のマニュアル作成: 62.3%(114人)
• 指針の定期的更新を行っている: 41.5%(76人)
(※日本プライマリ・ケア連合学会誌 2024, vol. 47, no. 2, p. 43-48 参照)
医療安全関連業務について棚卸
まずは、各クリニックで医療安全関連業務について棚卸しを実施しましょう!
クリニックにおいて医療安全を確保するためには、現状の業務を可視化し、どのような課題があるのかを整理することが重要です。以下のステップで棚卸を進めると、対応すべきポイントが明確になります。
- 現在の業務内容をリストアップ(例)
- 記録の作成・保管(診療録、インシデントレポートなど)
- 感染対策(消毒、マニュアル作成、スタッフ教育)
- 医薬品・医療機器の管理(使用状況の記録、点検)
- 個人情報保護(患者データの管理、アクセス権限の設定)
- スタッフ教育(研修、勉強会の実施状況、実施記録)
- その他
- 現状の課題を整理
- 現状の課題を整理するには、法令で定められている事と、現在の業務(状況)のギャップを確認する必要があります。
- 法令の確認には時間がかかりますが、株式会社MediCEが提供する簡易資料(※資料ダウンロードは、コラム下部の著者欄に掲載)を活用することで、効率的に整理が可能です。
棚卸し後に改善
- 改善の優先度を決める
- まずは法令遵守に必要なことは必ず実施する(Must) 急務・重要
- 法令義務ではないが医療安全として取り組むべきこと(Nice to have)
(例)無床診療所では、医療安全の委員会の設置は義務ではないが医療安全の改善のために委員会を設置して取り組む
- 実行計画を決める
- いつまでに?(期限)
- 誰が(担当者)
- どういった方法で改善するのか?(具体的なアクション)
効率的な改善していくためには、どういった方法で改善するのか?(具体的なアクション)がもっとも重要です。
よくある改善ポイント
法令義務化ドキュメントの不備
- 上記のプライマリケア学会の報告にもある通り、ドキュメントが用意されていないケースが多くあります。不足しているドキュメントは早急に作成が必要です。必要なドキュメントが不明な場合は資料をダウンロード(※資料ダウンロードは、コラム下部の著者欄に掲載)してご確認ください。
- 様々な団体から提供されているテンプレートを使用する場合、なるべく最新のものを利用することを推奨します。古いテンプレートには必要な要件が含まれていない可能性があります。
- 必ず施行年月日や改定日を記載し、更新履歴を明確にする。
- 自院に適した内容に修正し、運用しやすい形に整えましょう。
法令義務化ドキュメントの共有
- ドキュメントは準備しているがスタッフは見たことないというケースが非常に多いです。スタッフにしっかりと共有しましょう!
- 参考:医療安全管理指針、感染対策管理指針など指針はほとんどが共有することが義務付けられています。
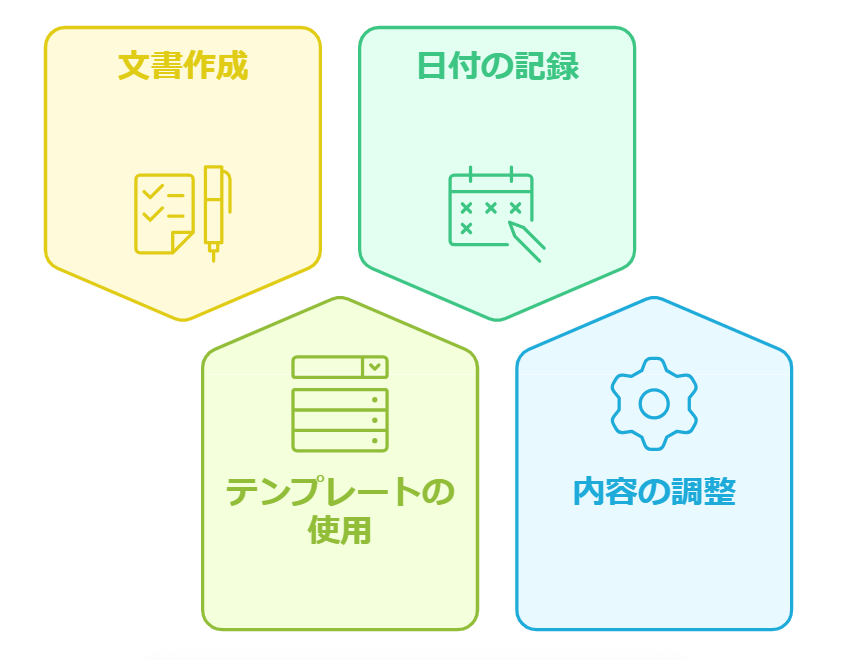
各種管理者や各種責任者の配置
- 正しく責任者や管理者を配置できていますか?決まってない場合は
- ダウンロードした資料を参考にし、必要な管理者・責任者を適切に配置しましょう。
- 参考:院長以外でも責任者を任命できる役割(例)
- 医薬品安全管理責任者
- 医療機器安全管理責任者
- 診療用放射線安全管理責任者
各種管理者や責任者の役割の実行
- 管理者や責任者はそれぞれの役割を適切に実施する必要があります。
- 院長は、各担当者が業務を遂行できるよう支援し、進捗を管理することが求められます。
講習の実施
医療安全や感染対策は、年2回の従業員への受講義務があります。これは必須の対応であり、未実施では済まされません。また、この講習は院長ではなく、職員(医療事務を含む)が受講する必要があります。
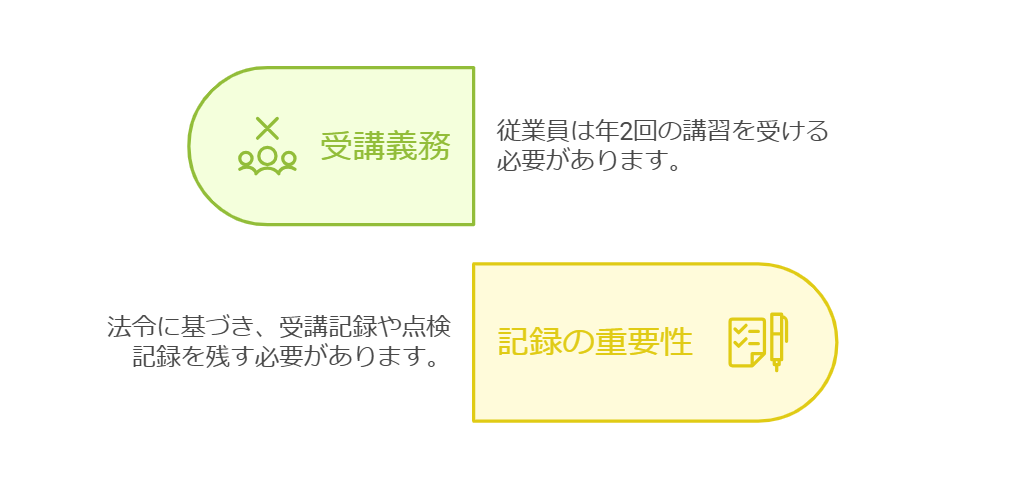
記録(ログ)を残す
- 受講記録や医療機器の点検記録など、記録(ログ)を残すことは法令で定められています。
- 様々な業界でログの電子化が進んでおり、クリニックにおいてもDX化による効率化を検討すると良いでしょう。
最後に
保健所の立ち入りには「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査」を十分に確認いただく必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001260077.pdf
ただ、日頃から患者様、職員の皆様の安全を考えしっかりと医療安全関連の法令に対応しておき、安全で健全なクリニック経営を心掛けておきましょう!
立ち入りの際、「クリニックパートナー360」※1のような院内ポータルシステムにより、ドキュメントを格納しておくと審査官の心証はよくなることの想像がつきますね。
■著者 株式会社MediCE 稲岡 稼頭斉
WEBサイト:https://medi-ce.com/
「医療環境に新しい価値と喜びを生み出し、医療の質を向上させることで、社会の豊かさに貢献する」 という理念のもと、医療従事者の皆様が安心して働ける環境をつくり、患者さんにとってより良い医療を提供できる仕組みを支えることに取り組んでいます。
※1 「クリニックパートナー360」
WEBサイト:https://medi-ce.com/agency/mekikiinosuke/wt1
Eラーニングを活用したスタッフ教育、インシデントレポートによる医療安全の向上、院内コミュニケーションの円滑化、業務効率化などを一つに統合
- 書類テンプレート機能を使って、医療安全に必要なテンプレートをダウンロードし作成可能
- 医療安全指針や医療機器の保守計画など、共有がスタッフに共有が可能
- Eラーニングによる医療安全・感染対策の受講とログ

資料ダウンロード(外部サイト):https://medi-ce.com/agency/mekikiinosuke/wt1
目利き医ノ助は、販売をしない “中立な立場 ” で、全国の先生のご要望や課題に合ったシステムのご提案や選定のお手