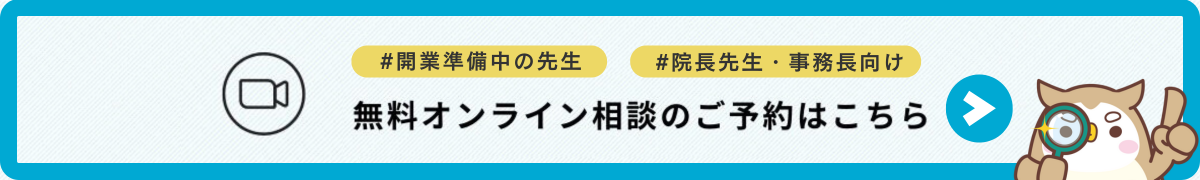2024.12.12
医療機関(クリニック・病院)のSNS運用が上手くいかない理由と解決策
SNSには媒体ごとに「できること」と「できないこと」が決まっています。その長所と短所を明確に把握して、使い方を間違えなければ、クリニックの経営に多大なメリットをもたらすことができます。
具体的には「6. SNS運用を効果的にする戦略」に記載しましたので、そちらをご覧下さい。
1. 医療機関でSNSを運用することの大切さと期待される効果
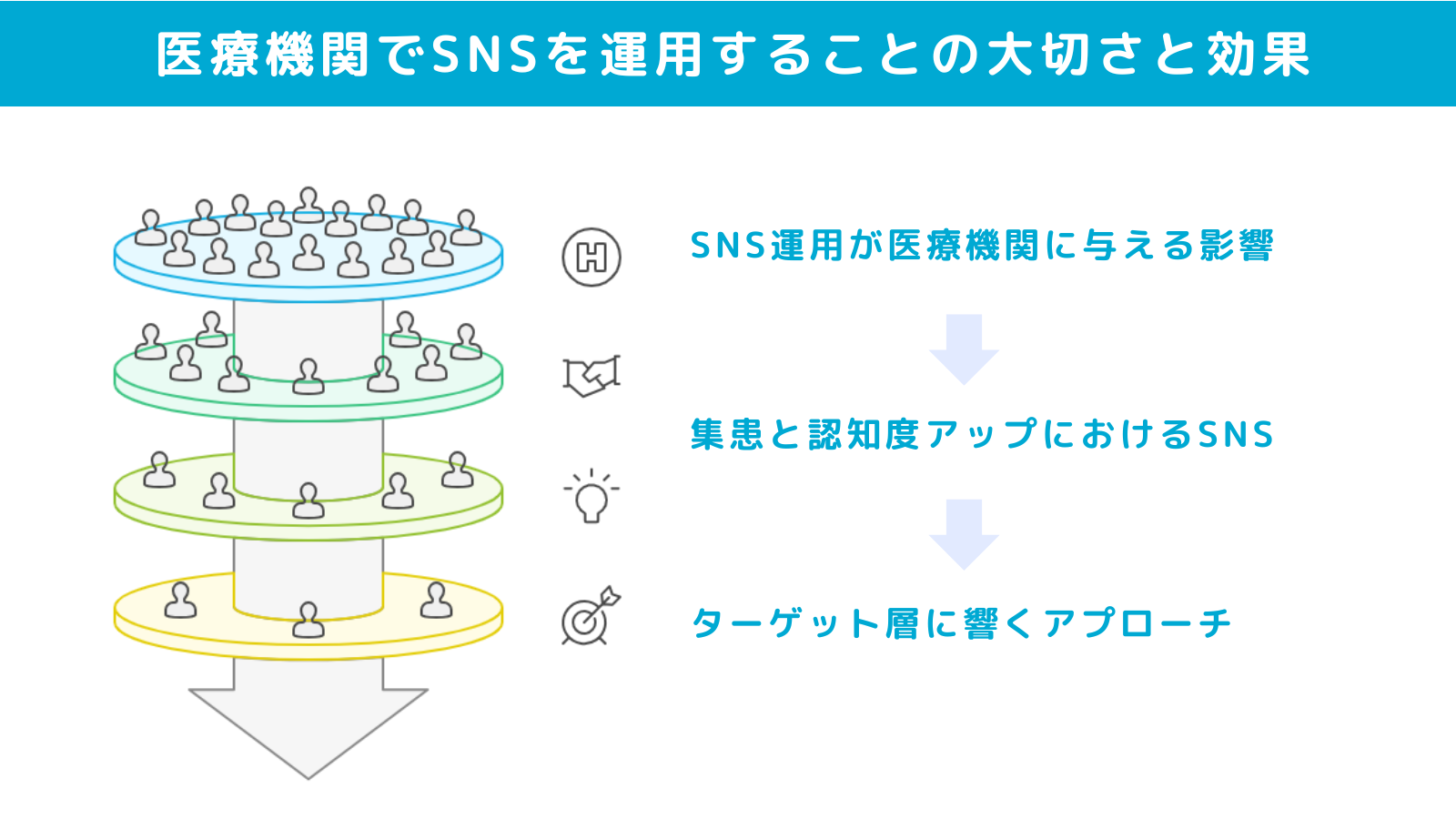
SNS運用が医療機関に与える影響
医療機関がSNSを活用すると、患者さんとの距離が縮まり、親しみを感じてもらいやすくなります。SNSを通して地域の方々に「通いやすそう」「安心できそう」といった印象を与えることで、自然とリピーターの増加や新たな患者さんの集患にもつながっていきます。
さらに、SNSを使って健康に関する情報や医師の知識を発信することで、患者さんの健康意識を高める手助けができるのも魅力です。予防医療に役立つ知識やちょっとした豆知識を提供することで、医療機関の役割を広げることができるのもSNSならではのメリットといえます。
集患と認知度アップにおけるSNSの効果
SNSは多くの方が日常的にチェックしているツールで、特に若い世代や働き盛りの世代には、チラシやポスターよりも効果的に情報を届けられます。また、SNSの投稿がうまく反響を呼べば、短期間で一気に多くの人へと認知を広げることも可能です。
そして、SNSでの情報発信を通じて「このクリニックなら信頼できる」と思ってもらえれば、口コミやシェアによってさらに多くの人へと広がっていきます。こうした信頼を積み重ねていくとフォロワーも増え、新しい患者さんの来院にもつながりやすくなるのです。
ターゲット層に響くアプローチ方法
SNS運用を成功させるためには、発信したいターゲット層に合わせた内容が欠かせません。たとえば小児科なら子育て世代の親御さん向けの情報、整形外科なら中高年層が関心を持つ内容など、医療機関の専門性に応じて投稿を工夫することで、フォロワーの方々からも親しみを持ってもらいやすくなります。
適切なターゲット層に向けて情報を発信すると、届けたい内容が自然と効果的に伝わり、来院につながる可能性も高まります。読者が抱えている健康に関する悩みや興味に応える投稿を続けることで、SNSを通じて信頼関係を深めていけるでしょう。
2. 医療機関が直面するSNS運用の課題とは?
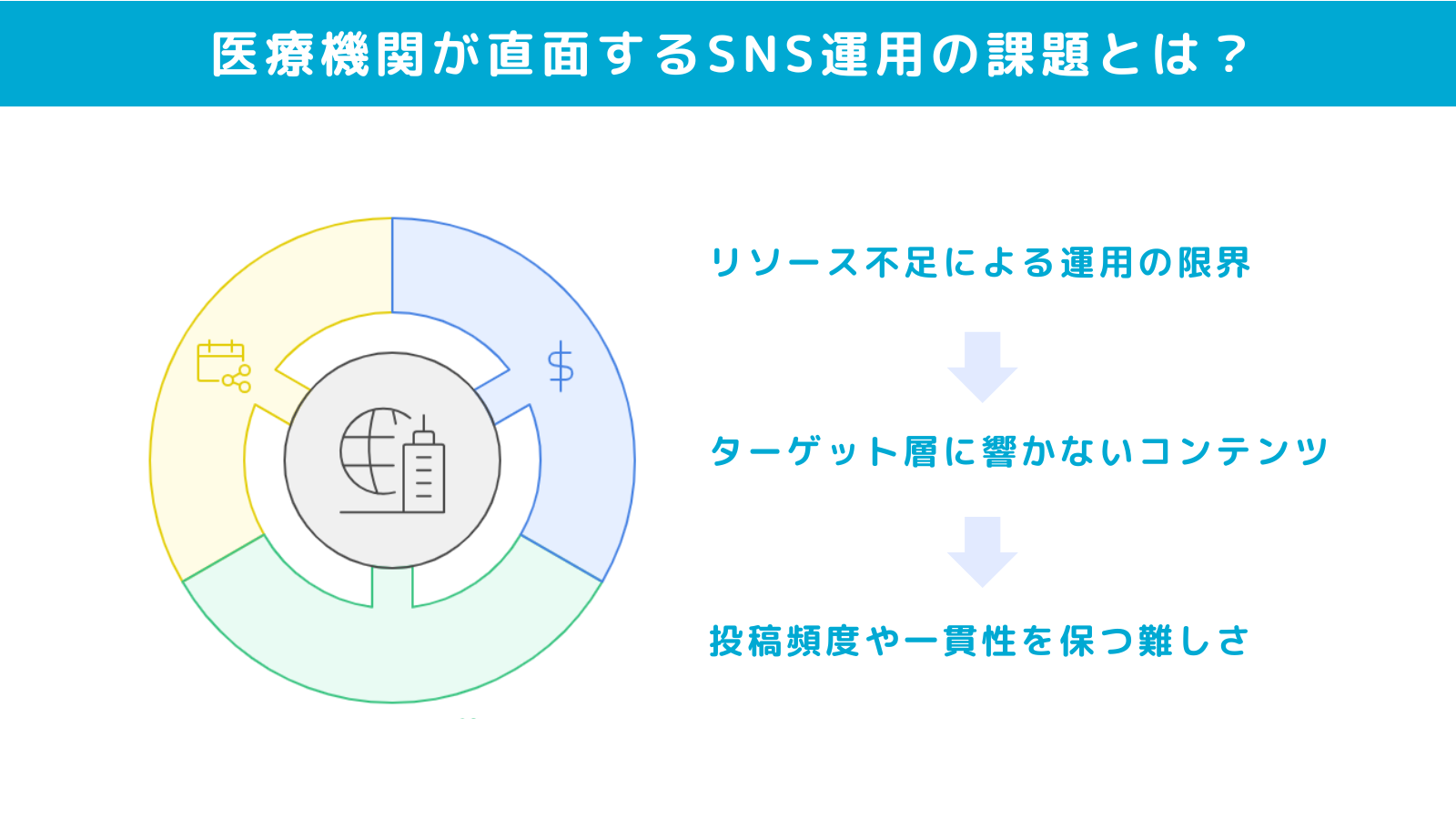
リソース不足による運用の限界
多くの医療機関では、SNS運用を専任で行うスタッフがいないため、日々の業務とSNS投稿を両立するのが難しいと感じることが多いようです。医師や看護師が忙しい業務の合間を縫って投稿を考えるのは負担が大きくなりがちですし、頻繁に更新できないと感じているケースも少なくありません。
こうしたリソース不足が原因で、せっかくSNSを始めても投稿が続かず、結果的に認知度や集患への効果が薄れてしまうこともあります。
ターゲット層に響かないコンテンツ
SNSの投稿内容が、ターゲットにしっかりと響くものでなければ、思ったような反応が得られません。医療機関のSNS運用では、患者さんが求める情報に寄り添ったコンテンツが必要です。しかし、どうしても専門的な内容に偏りがちで、読み手にとっては難しく感じられることもあります。
たとえば、診療内容の紹介や治療法の説明だけでなく、患者さんの日常生活に役立つ情報や予防に関するアドバイスを含めることで、患者さんが「ためになる」と感じられる投稿が可能になります。
投稿頻度や一貫性を保つことの難しさ
SNS運用では、定期的な更新が重要です。しかし、医療機関では日々の診療が忙しく、SNS投稿にまで手が回らないことも少なくありません。その結果、更新が途切れがちになり、フォロワーの関心が薄れてしまうことがあります。
投稿が続かないと、フォロワーに「このクリニックはアクティブじゃないのかな?」と思われてしまうこともあるため、コンスタントな投稿がSNS運用における一つの課題といえます。
3. SNS運用が失敗する主な原因とその背景
ターゲット層の設定ミスと認識のズレ
SNS運用で成果が上がらない理由のひとつに、「ターゲット層が曖昧」という点が挙げられます。例えば、対象とする年齢層や生活スタイルに合わない内容を発信してしまうと、フォロワーが興味を持ちづらくなります。SNSの特性に応じたターゲット設定がしっかりしていないと、フォロワーが定着しにくくなることも少なくありません。
クリニックの専門分野に合わせて、ターゲット層をしっかりと見極め、内容をチューニングすることが大切です。例えば小児科なら「親御さんが安心できる内容」、内科なら「生活習慣病予防の知識」といった、患者さんが求める情報を意識していくと効果的です。
投稿内容が医療機関のブランディングと不一致
SNS運用では、クリニックの「イメージ」を伝えるのも大切なポイントです。しかし、投稿内容がブランディングとズレてしまうと、「何を大切にしている医療機関か」が患者さんに伝わりにくくなります。例えば、アットホームな雰囲気を打ち出したいなら、硬い内容だけでなく、柔らかく親しみやすい投稿も含めることで、フォロワーがクリニックの雰囲気を感じやすくなります。
一方で、専門性の高さをアピールしたいなら、信頼感のあるしっかりとした内容を中心にすることも効果的です。SNSを通じてクリニックの個性を発揮することが、フォロワーにとっての魅力になります。
継続的な運用が難しくなる理由
医療機関では、日々の診療業務が最優先のため、SNS運用が後回しになりやすいのが現状です。特に、運用担当者が忙しい場合、投稿の計画を立てるのも簡単ではありません。その結果、更新が止まってしまい、せっかく増えたフォロワーが離れてしまうことも考えられます。
SNS運用を長く続けるには、無理のない運用方法を工夫することが大事です。例えば、週に1〜2回のペースで投稿する計画を立てる、定番のコンテンツを決めておくといった工夫をすることで、忙しい中でもSNSを続けやすくなります。
4. 医療機関が成果を出すためのSNSコンテンツのポイント
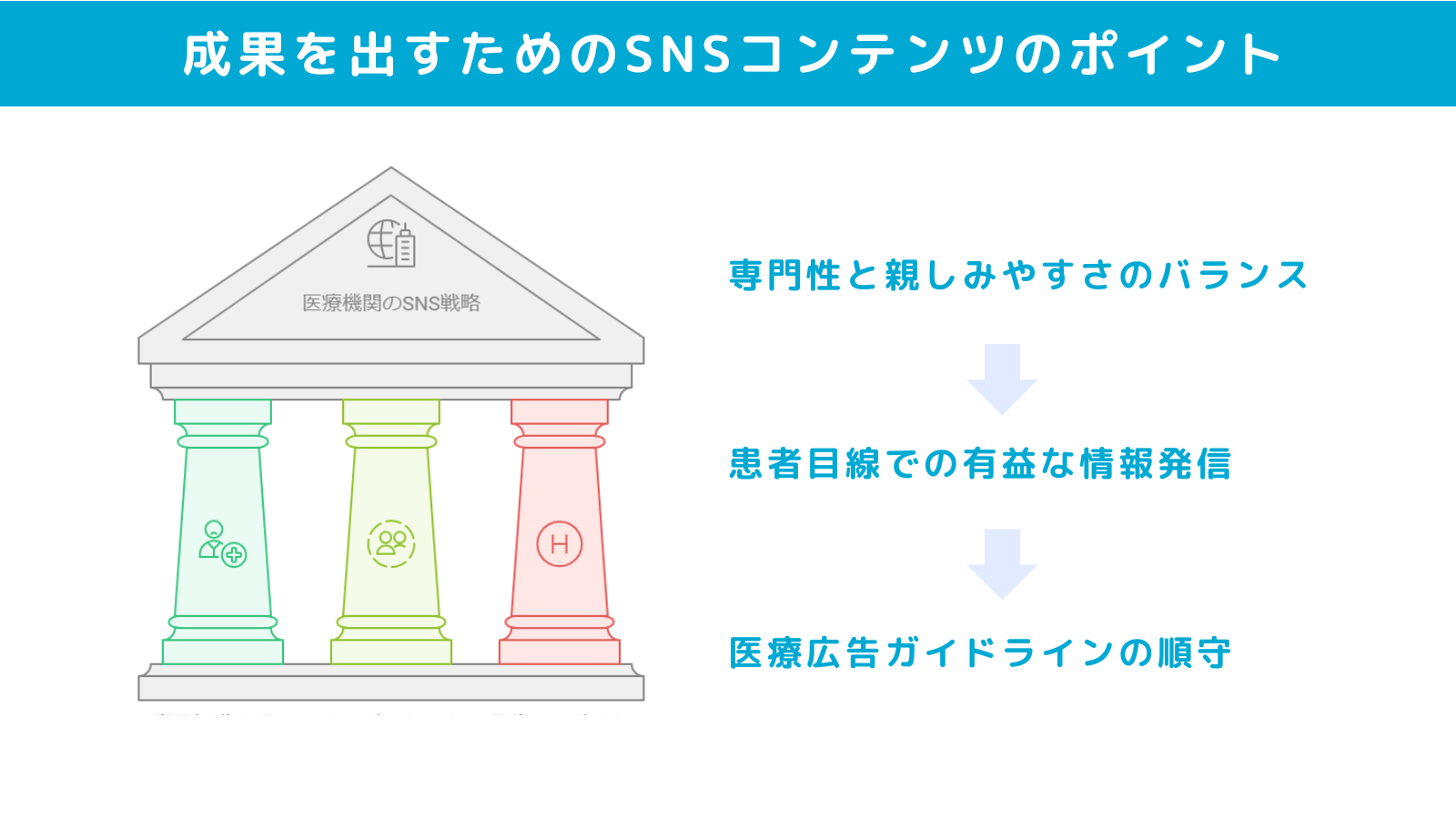
専門知識と親しみやすさのバランス
医療機関がSNSで成果を上げるためには、「専門的な内容」と「親しみやすさ」をうまく組み合わせることが大切です。専門的な情報は、信頼感を高めるために必要ですが、難しい言葉ばかりでは読むのが負担になります。そこで、わかりやすい表現やイラスト、写真を使って、情報を伝わりやすく工夫することが重要です。
例えば、「インフルエンザの予防法」や「子どもの健康管理のポイント」など、身近なテーマを簡単に紹介することで、読者が気軽に読むことができます。また、医療機関の雰囲気が伝わるようなスタッフの写真や施設の紹介を交えると、より親しみやすくなります。
ターゲットに合わせた有益な情報発信
SNS運用では、ターゲットとなる読者が「ためになる」と思える内容を発信することがカギです。小児科なら育児に役立つ情報、整形外科ならリハビリや運動に関する知識など、専門性を活かしながら、読者が日常生活に取り入れられるような内容が効果的です。
例えば、「日々の生活で簡単にできる腰痛予防のストレッチ」や、「子どもが風邪をひかないためのポイント」など、具体的で取り組みやすい内容にすると、フォロワーも「これならやってみよう」と思いやすくなります。
医療法に基づく情報発信のガイドライン
医療機関がSNSで情報を発信する際には、医療法に基づいた「医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)」を守ることが必要です。過度な宣伝や誤解を招く表現は避け、正確で信頼性のある内容を意識することで、フォロワーに安心してもらえます。
医療法では、誇大広告や過剰なアピールが禁止されていますが、適切な情報発信は推奨されています。医療機関としての信頼感を守りつつ、フォロワーにとって役立つ情報を丁寧に提供することで、SNSが効果的な集患ツールとなります。
5. 成功事例から学ぶ!医療機関におけるSNS活用術
成功事例から見る患者との信頼関係の築き方
SNSを通じて患者さんとの信頼関係を築くためには、医療機関の「らしさ」が伝わる内容を意識することが大切です。例えば、日々の診療の様子やスタッフの笑顔が見える投稿、季節ごとの健康アドバイスなど、クリニックの日常を垣間見せるような内容は、患者さんに親しみを感じてもらいやすくなります。
例えば、小児科のSNSでは「お子さんの健康について安心して相談できるクリニック」というイメージを持ってもらうため、親しみやすいイラストや短文でのテキスト投稿が忙しい親御さんに好評です。
地域密着型のアプローチとその効果
地域に根ざした医療機関にとって、SNSは地域の方々とつながる有効な手段です。例えば、クリニックが開催する健康セミナーの案内や、地元のイベント情報を共有するなど、地域に密着した内容を発信することで「地元の医療機関」としての認知度が高まります。
実際、地域の人々との関係が強い医療機関では、SNSで「いつも通っているクリニック」という親しみを持ってもらうことで、来院のきっかけや信頼の構築にも役立っているようです。
他の医療機関との差別化戦略
SNSでは、医療機関の特徴や強みをしっかりアピールすることで、他院との差別化が図れます。例えば、整形外科なら「リハビリ設備が充実している」「専門スタッフによる運動指導が受けられる」といった具体的な情報を発信することで、患者さんに「ここなら自分に合っている」と感じてもらいやすくなります。
また、診療方針やクリニックの理念を紹介する投稿も効果的です。「患者さんの声に耳を傾ける」「丁寧な診察を心がける」といった姿勢をSNSで伝えることで、他の医療機関にはない独自の魅力を感じてもらうことができます。
6. SNS運用を効果的にする戦略とは
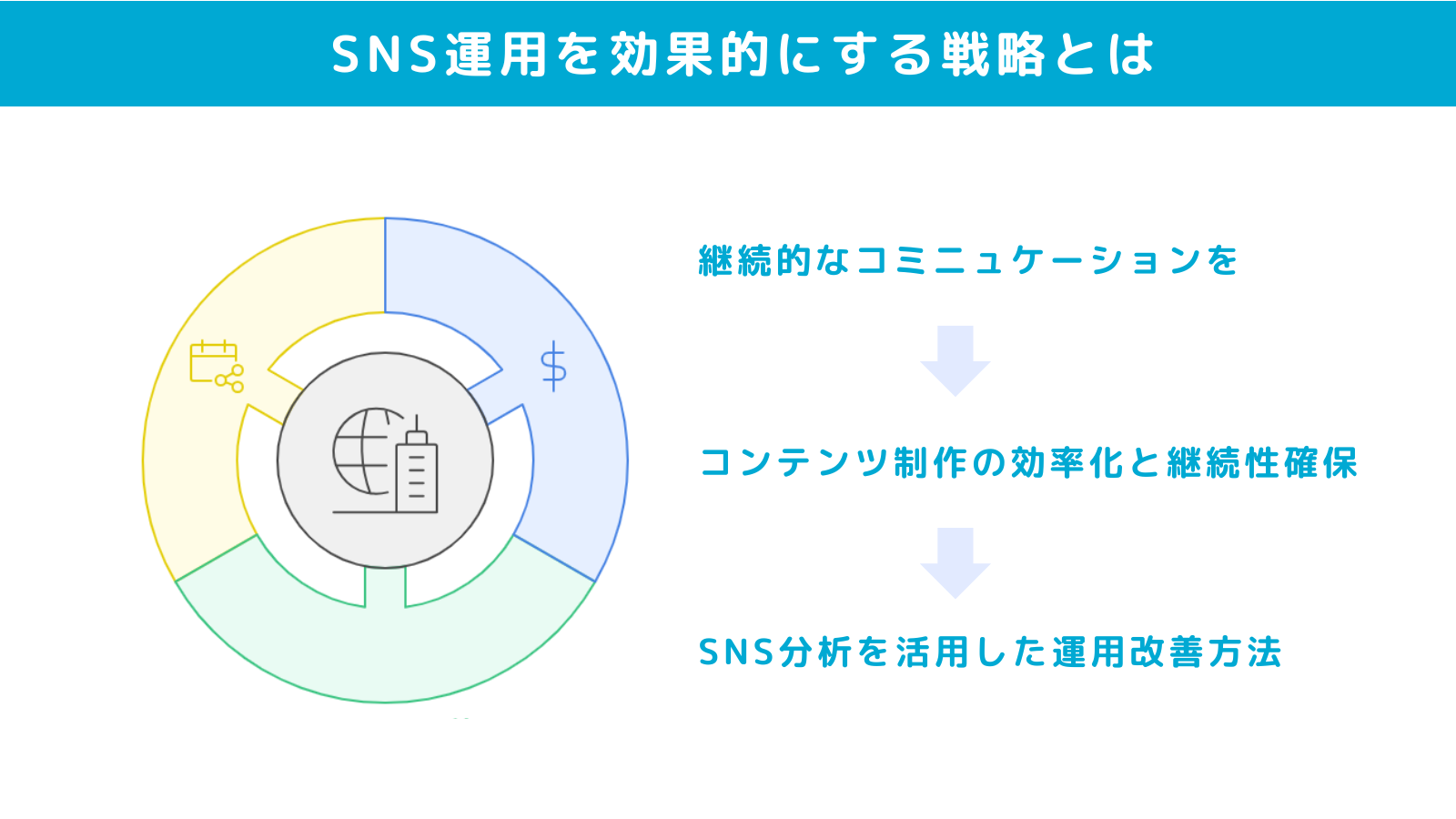
クリニックがSNSの運用を成功させるためには、ひとつのプラットフォームに1つの役割を持たせるという考え方が大切です。医療機関(病院・クリニック)には、特に次の3つの組み合わせがお勧めです。
- X(旧Twitter)
- note
- LINE公式
X(旧Twitter)で「認知度」を高める
例えば、X(旧Twitter)には認知度(impression)を上げる役割があります。
人間には繰り返し見る回数が増えると好感度が増すという性質があり、この心理的効果は「ザイオンス効果」と呼ばれています。X(旧Twitter)は、投稿する内容によって異なりますが、一般的なポスト(ツイート)は140文字以内に制限されています。ですから、読者を感動させて好意度を向上させることには向いていません。X(旧Twitter)は、「ザイオンス効果」を意識して、繰り返し発信して認知度(impression)を上げる役割を持たせると効果的です。
noteで好感度アップ
文字数制限のあるX(旧Twitter)に対して、noteは長文の記事をつくれるのが強みです。それを活かして日々の診療に込めている医師やスタッフの想いをダイレクトに伝えることができます。そのため読んだ人に愛着をもってもらったり、感動してもらったりするのが得意な媒体といえます。
ところで最近、クリニック内のほんのちょっとした言葉や態度の行き違いから、Googleレビューなどで低い点をつけられ困惑している医師や医療関係者が少なくありません。こうした行き違いを解くには、医師やクリニックの想いをダイレクトに伝えることができるnoteという媒体がぴったりです。
実際にnoteを運用しているクリニックには「こんな先生に診てもらいたい」「こんな素晴らしい先生に診てもらえる地域の方がうらやましい」など高評価のコメントが多数寄せられています。
またnoteはもっとも炎上しにくいSNSでもあります。悪意のあるコメントや誹謗中傷のコメントが寄せられた場合は、運営側で削除することができます。それだけでなく、コメントを寄せた側には削除されたことが通知されない仕組みになっているので安心です。
そしてnoteには、お金をかけて表示数を高める「広告機能」がないのも特長です。広告機能は資本力のある組織に対して有利に働きますが、そうした機能がないことで誰でも平等にコンテンツ力で勝負ができます。コンテンツ力がそのまま好感度アップにつながるのもnoteの長所です。今からはじめても質の高いコンテンツを掲載すれば、たくさんの人に自院の記事を読んでもらうことができます。
noteに弱点があるとすれば、拡散力が他のSNSにくらべて弱い点でしょうか。
LINE公式アカウントで継続的なコミニュケーションを
3つめにお勧めするLINE公式アカウントは、一度来院されたことのある患者さんに継続的なコミュニケーションをとるためのSNSです。
多くのクリニックは、一度来院された患者さんは再び来院されるものと期待しているのが現状です。ところが、周囲にはつぎつぎと新しいクリニックが開業しており、そちらに流れていく患者さんも少なくありません。
これを防ぐためには、一度来院された患者さんに再び医療ニーズ(症状・疾患)が発生する前にマーケティングコミュニケーションを取る必要があります。LINE公式アカウントはそのためのSNS媒体にぴったりです。
LINE公式アカウントを使って定期的に情報発信することで、リピーターの患者さんが増えるだけでなく、親しい人などにクリニックの良さを伝えてくれることも期待できます。
こうした役割はメールマガジンなどでも果たせますが、メールは埋もれがちでそもそも気付いてもらえません。その点日常生活に浸透しているLINEを使ったSNSであるLINE公式アカウントは多くの人に使ってもらいやすいのも強みです。
LINE公式アカウントの弱点をあげるとすれば、「友達登録」をしてもらわないとメッセージが届かないことでしょうか。
LINE公式アカウントをクリニックで運用する効果は?活用事例や注意点を解説!
SNSの長所をうまく掛け合わせる
SNSはそれぞれ長所と短所をもっています。ですからその長所をうまく掛け合わせることが大事です。
ここで紹介した3つのSNSであれば次のようになります。
まずX(旧Twitter)でユーザーから認知度を高め、それからnote記事に読者として誘導して好感度を高めます。そして一度来院された患者さんにはLINE公式アカウントで継続的なコミュニケーションをとっていく。
こういう媒体同士のかけ算を意識したSNSの使い方が大事です。
コンテンツ制作の効率化と継続性確保
SNS運用が続かない理由のひとつが「投稿する内容を考えるのが大変」という点です。そのため、事前にテーマや内容を決めておくことで、コンテンツ制作がスムーズになります。例えば、毎週決まった曜日に「健康に関する豆知識」や「季節の病気対策」を発信するなど、定番の投稿スタイルを作ることで、内容を考える負担が減り、無理なく続けられます。
また、まとめて投稿内容を作成し、予約投稿機能を使って定期的に投稿されるようにしておくと、忙しい日でも更新が途切れず、フォロワーの関心を引き続けることができます。
SNS分析を活用した運用改善方法
SNS運用の効果を高めるには、定期的にフォロワーの反応を確認し、投稿内容を改善していくことが大切です。いいねやコメント、シェアの数を分析することで、どんな内容がフォロワーに響いているのかを把握できます。たとえば、健康に関するアドバイスが多くの反応を得ているなら、その分野の内容をさらに充実させるといった調整が可能です。
また、フォロワーの年齢層や関心のあるテーマなども分析できるため、クリニックのSNSに求められているものを把握しながら改善を続けていくと、より効果的な運用が期待できます。
7. SNS運用を支えるサポート業者の活用方法
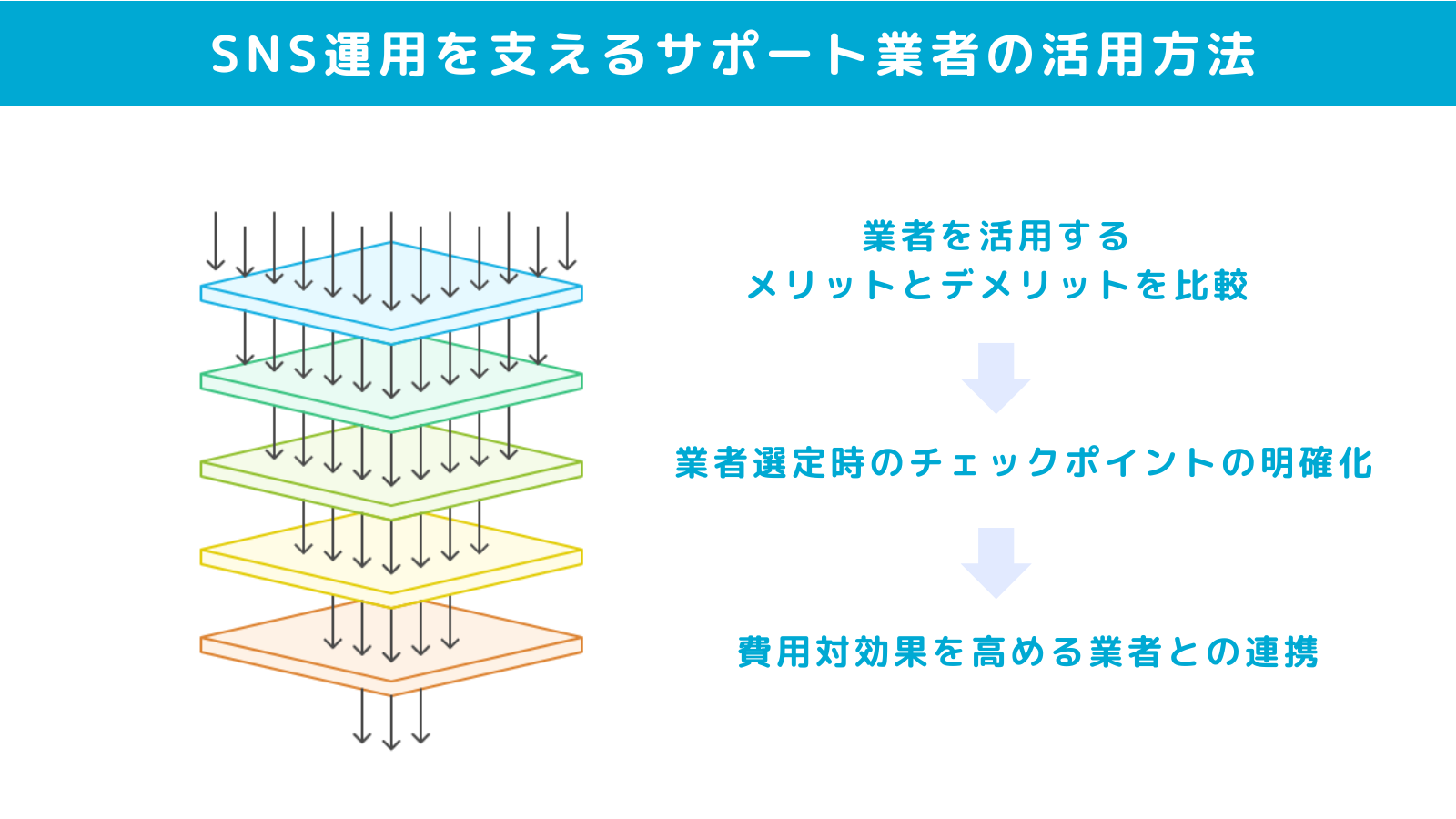
サポート業者を活用するメリットとデメリット
SNS運用を専門のサポート業者に依頼することで、医療機関は診療に専念しながらも、SNSを効率的に運用できます。業者にはSNS運用のノウハウがあり、効果的なコンテンツ制作やターゲットに合った戦略の提案が可能です。特に、医療業界のガイドラインや専門的な表現に配慮した発信が必要な場合には、プロのサポートが役立ちます。
ただし、業者に依頼する場合、費用が発生するため、そのコストに見合った効果が得られているかを常に確認する必要があります。また、医療機関の方針や雰囲気がうまく反映されているかをチェックしながら、運用の方向性を調整することが大切です。
業者選定時のチェックポイント
SNSサポート業者を選ぶ際には、医療業界に特化した経験や実績があるかが重要です。医療関連の情報発信には細かなルールがあるため、これを熟知している業者であれば安心して依頼できます。また、過去の運用実績や提案内容を確認し、医療機関が求める内容に適したサポートが提供できるかを見極めることが大事です。
さらに、業者とのコミュニケーションがスムーズに取れるかどうかもチェックしておきましょう。医療機関の意向をきちんと反映してもらえるかが、成果を上げるためのカギとなります。
SNSのサポート業者はほぼ間違いなく自社のSNSアカウントを運用していますので、そこから実力をみることも重要です。
費用対効果を高める業者との連携法
サポート業者と連携してSNS運用を行う場合は、費用対効果を高めるための工夫がポイントです。たとえば、業者にすべてを任せるのではなく、医療機関側でもアイデアを出し合い、患者さんの声を取り入れたコンテンツを作成することで、オリジナリティを高めることができます。
また、定期的に運用の成果を確認し、業者とともに戦略を見直していくことで、SNSの運用がより効果的に進むでしょう。双方が連携してクリニックの特徴を活かしたSNS運用を行うことで、患者さんとの距離を縮めることができ、集患や認知向上にもつながりやすくなります。
8. SNS運用を成功させるための最終チェックリスト
運用の進捗を見直すタイミング
SNS運用は、始めたら終わりではなく、定期的に見直しと改善が必要です。毎月または四半期ごとに成果を確認し、目標に対する進捗をチェックすることで、効果的な運用を続けられます。もし目標に届いていない場合は、ターゲットや投稿内容を再調整し、次の改善に役立てましょう。
投稿内容とフォロワーの反応分析
フォロワーの反応を確認しながら、投稿内容が求められている情報かを分析するのもポイントです。いいねやコメント、シェアが多い投稿には共通点があるはずなので、それをもとに今後の投稿内容を考えると、より効果的な運用が期待できます。
持続的な改善のためのPDCAサイクル
SNS運用の成功には、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)というPDCAサイクルの導入が役立ちます。定期的に運用の進捗や反応を振り返り、次の投稿や戦略に活かすことで、継続的な成長が見込めます。このようなサイクルを意識することで、患者さんにとって価値のある情報を提供し続けることができます。
クリニックにおけるSNS運用は多数のメリットあり!検討時は専門家に相談を
SNSはクリニックにとって大変便利なシステムです。使いこなせば集患効果や採用効果・業務効率化などが見込め、そのメリットは計り知れません。
しかし、運営には注意が必要です。特に開設・運用作業を誰がやっていくかによって得られる効果が変わります。SNS運用に興味がある方や、導入を検討しているものの開設者がいないクリニックなどは専門家に相談するのもひとつの方法です。
目利き医ノ助はクリニック向けITシステム等の目利きのプロ集団です。クリニックの状況やご希望に応じて最適な選定をサポートをさせていただきます。SNS運用についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。